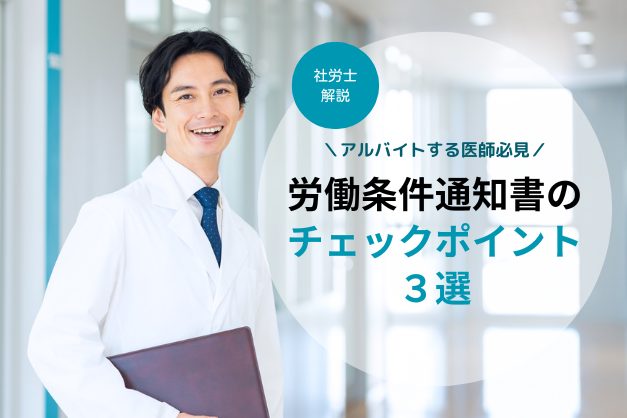
労働条件通知書は、入職前に労働条件を最終確認するための重要な書類です。アルバイトを始める前に、労働条件通知書で契約内容を確認することは法的に義務付けられています。契約期間、賃金、労働時間などが書面で明示され、特に契約更新や社会保険加入、退職時のルールについて確認が必要です。使用者からの解雇には合理的な理由が求められ、退職を申し出る際は早めの通知が推奨されます。書面での労働条件確認は、労働者の権利保護に役立ちます。
本記事では特定社会保険労務士の舘野聡子先生に、医師がアルバイトの雇用契約時や入職後にトラブルになりやすいポイント、そしてトラブルを回避するために労働条件通知書でチェックすべきポイントを伺いました。
労働条件は、アルバイトを「始める前に」「書面で」確認しよう
「労働条件通知書の交付」は、法律で義務付けられている
舘野:トラブルを回避するためには、アルバイト先に入職する前のタイミングで、労働条件を書面で確認することが非常に大切です。
労働基準法第15条には、以下のような記載があります。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
引用:e-GOV法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」
編集部:雇用契約を結ぶ際、使用者は労働条件を明示する書面(労働条件通知書)を労働者に交付することが義務付けられているということでしょうか?
舘野:その通りです。
お互いのルールを明文化した労働条件通知書がない場合、使用者が一方的にルールを解釈して労働者を使用してしまう可能性も考えられますよね。
そのため労働基準法では「使用者の立場の方が強い」という前提に立ち、労働者の権利を守るという意味合いも含めて、労働条件通知書の交付を使用者の義務としています。
編集部:口頭ではなく書面で労働条件が示されていることは、労働者にとっても大きな安心感につながりますね。
舘野:そうですよね。
労働条件通知書は、内定時など交付されるケースが多いようですが、もし入職する前に受け取れないようであれば、使用者に確認・相談してみることをお勧めします。
現在は、FAXやメール、SNS等で労働条件を明示することもできます。
労働条件について明示すべき事項は、法律で定められている
舘野:労働基準法施行規則第5条第1項では、使用者が労働条件通知書で必ず労働者へ通知しなければならない事項が決められています。
具体的には、以下の6項目がそれに該当します。
書面の交付により明示することが義務付けられている事項
・契約期間(有期契約、または無期契約)
・就業の場所
・従事すべき業務の内容
・始業・就業の時刻、残業、休憩時間、休日・休暇(年次有給休暇含む)
・賃金(支給額、計算方法、締め日、支払日、支払い方法に関する事項)
・退職に関する事項(自己都合退職の手続き、解雇の事由および手続き)
要件を満たせば、アルバイト医師にも有給休暇が付与される
編集部:上記の「休暇」という項目で年次有給休暇についての記載がありますが、アルバイトとして働く場合にも有給休暇が付与されるのですね。
舘野:年次有給休暇は、正社員・パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して付与されます。
具体的には、「雇入れの日から6か月継続勤務」「全労働日の8割以上出勤」という2つの要件を満たした場合、年次有給休暇が発生します。
付与日数など詳しい情報は、以下でご確認ください。
参照:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
アルバイトの雇用契約時に、医師が注意すべき3つのポイント

編集部:続いて、アルバイトで雇用契約を結ぶ際や入職後にトラブルになりやすいポイントや、回避するための対策があれば教えてください。
舘野:アルバイトの雇用契約を結ぶ際や入職した後でトラブルになってしまうことが特に多いのは、以下の3つのポイントです。
医師アルバイトでトラブルになりやすいポイント①契約更新
舘野:契約期間について「あまり気にしたことが無かった」という先生も多いのではないかと思いますが、実はトラブルになりやすいポイントのひとつです。
この契約期間には、契約期間の定めがない「無期雇用契約」と、契約期間の定めがある「有期雇用契約」があります。
編集部:医師のアルバイトの雇用契約では、1年程度の「有期雇用契約」、もしくは期間の定めなしの「無期雇用契約」が多い印象があります。
舘野:ここで気を付けておきたいのは、雇用契約時に交付される労働条件通知書内に更新に関する取り決めが明示されているかどうかです。
入職前のタイミングで契約更新に関する認識合わせがしっかりできていないと、「引き続き勤務するつもりだったのに、雇い止めで働けなくなってしまった」といったトラブルに発展してしまうかもしれません。
特に、雇用期間の定めがある有期雇用契約を締結する際には、労働条件通知書内に
・契約更新の有無(契約を更新しないことがあるかどうか)
・契約更新有無の判断基準
が記載されているか、しっかり確認しておくと良いですね。
▼関連記事
医師アルバイトでトラブルになりやすいポイント②社会保険加入
舘野:また社会保険加入に関する事項も、入職前に確認しておくと安心な事項です。
実は、社会保険に加入する・しないということは労働基準法上の労働条件には該当せず、労働条件通知書への記載は義務となっていません。
そのため、社会保険加入に関する記載がない労働条件通知書もあるかもしれません。
ただ、社会保険に入るかどうかは労働者にとって大きな関心事です。
もし社会保険加入の対象とならない場合も、労働条件通知書にその旨の記載があるとなお良いでしょう。
編集部:確かに 非常勤の場合も、一定の要件を満たすことで社会保険に加入できるケースがありますよね。
週3日や4日勤務などの非常勤で働く先生にとっては、特に気になるポイントだと思います。
▼関連記事
医師アルバイトでトラブルになりやすいポイント③解雇・退職
舘野:最後にご紹介する解雇・退職に関する事項も、不安や迷いが生じやすく、トラブルに発展しやすいポイントです。
編集部:せっかく勤務してきたアルバイト先ですから、できる限り円満に退職したいと思う方も多いのではと思います。
解雇や退職に関するルールは、法律上どのように定められているのでしょうか?
舘野:使用者から労働者への一方的な労働契約の終了のことを解雇といいますが、これは使用者がいつでも自由に行えるものではありません。
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできないと定められています。
つまり、医療機関が医師を解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
編集部:実質、使用者が労働者を解雇することはかなり難しいということでしょうか。
舘野:そうですね。
もし解雇の合理的な理由が認められる場合にも、労働基準法第20条では以下のような措置を講じることが定められています。
・解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要がある
・予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない
・予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要がある
参照:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
編集部:反対に、自分から「アルバイトを辞めたい」と思った時については、どのようなルールがありますか?
舘野:その契約が有期雇用契約なのか、無期雇用契約であるかによって異なります。
まず働く期間を入職前に双方で定める有期雇用契約では、「やむを得ないが事由」が無い限り、契約期間中は契約を終了させることができません。
一方の、働く期間の定めがない無期雇用契約では原則として、退職をいつでも申し出ることができます。
ただし急に医師が退職をしてしまうと、アルバイト先に大きな迷惑が掛かってしまいます。
加えて医師の場合、その職業上の特性などから「その医師がいないと、診療が成り立たなくなってしまう」というケースも十分あり得るでしょう。
トラブルを回避して円満に退職したい場合は、「退職の1か月前までに申し出ること」といった入職時に双方で定めたルールに則って、できる限り早いタイミングで退職の申入れをするよう心がけたいところです。
なお民法では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職届を提出するなど退職の申入れから2週間で退職できるとされています(民法第627条第1項)。
編集部:お互いが決めたルールに従って明確に退職の意思表示を行ったうえで、勤務先の状況もしっかり考慮しながら、余裕を持って退職日を相談できると良いですよね。
舘野:そうですね。
退職に関する事項をはじめ、医師のアルバイトでトラブルになりやすい局面では、労働条件通知書内に記された「お互いのルール」が非常に重要になってきます。
入職後のご自身を守るために、そして安心してアルバイトをするために、労働条件通知書が交付される入職前のタイミングで、不安なことや疑問点をクリアにしておくことをお勧めします。
「医療機関への確認は、何だか気後れしてしまう」「この記載は妥当なのか、分からない」
アルバイト入職時のお困りごとがある先生は、医師のアルバイト探しのサポート経験が豊富なDr.アルなびのコンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。








